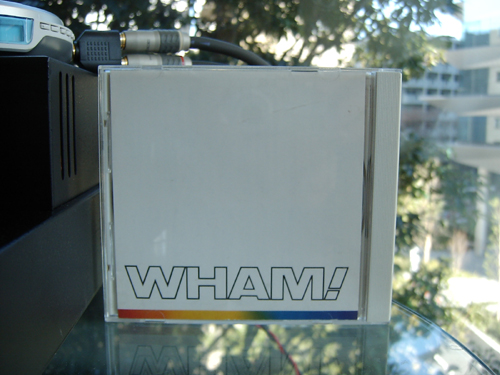|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和生まれの人間にとって、CDが発売された頃、デジタル音源とは何かとの説明で良く聞かされたのは、電話と電信の違いだった。電話は音圧の連続的変化で、電信はトン・ツーのたった長短二種類の音で情報を伝達する原理だった。当然の事、多くの情報を伝えられるのは音圧の連続的変化の方だが、それ故に余計な雑音も一緒に送ってしまう欠点がある。それに比べトン・ツーの二種類(デジタル技術では0と1)だと雑音は含まれないが、短時間に多量の情報を送る事はできない。音圧のアナログ的変化はアップダウンの連続する坂道だが、デジタルでこれを表すとアップダウンの連続する階段になる。階段の数が少ないとガタガタ道になってしまうので、これを如何に滑らかにするかと言うと階段の幅を小さくして数を増やす事になる。 CDでは1秒間を44100回に分けて(44.1KHz)て階段の幅を決め、0と1を使って16bitで表される2進数の値で階段の高さを決めている。16bitとは16個の電源端子に、それぞれ電気が来ているかいないか0と1の組み合わせの2進数で音圧を表している。CDの再生できる高域の周波数の上限は20KHzと表示されている。それはサンプリング周波数が44.1KHzなので、それ以上の高音は絶対に録音再生出来ないのが解るが、音の忠実さの再現から、その半分程度の周波数が再現性の限界になるからだろう。 最近話題のハイレゾ音源とは、サンプリング周波数を88.2、96、192KHz、24bitで録音再生するシステムなのだ。階段の幅を細かくし、高さはより細かく正確に記録できる工夫がされている。デジタル技術は日進月歩で凄い事になってきているのだが、何故今になってカセット・テープとかLPレコードとか昔のアナログ音源に注目が行っているのか考えてみた。 ハイレゾ音源と言っても、原音により近づく工夫はしてあるが、階段状のデジタル方式で録音されている都合、アナログに変換した再生音は擬似音にすぎない。表面がザラ付いている壁の表面をデジタル・データーと考えると、パテを使って表面を滑らかにする下塗りが必要だ。パテを使って表面仕上げをし、見るに耐えないザラ付いた面を綺麗に仕上げる左官屋さん役がDAコンバーターと呼ばれる回路で、デジタル・データーをアナログ・データーに変換し、数値の羅列を人が聞こえる音に戻しているのだ。 当方の子供の頃は音楽の先生の弾くオルガン演奏から始まって、商店街を練り歩くチンドン屋とか、生の演奏を聞く機会は珍しくなかった。先日、麻布十番商店街でチンドン屋の一行と出会ったが、腹に響く強烈な生の楽器の音は久々に衝撃的だった。生演奏聴いたことのない若い世代の方々がそれを聴いたら、ショックに近い感動を得るに違いない。 <2016/2/2>音のファクターには音の高低を決める周波数、音の大きさの音圧、音色を決める波形がある。CDで再生できる高域の周波数は20KHz、これは人間の聴ける高音は20KHzが限界で、それ以上は聴こえない事から決められたらしい。しかしハイレゾ音源は20KHz以上の聴こえない筈の高域の再生をしている。20KHz以上の超音波を使って生活しているコウモリやイルカではあるまいし、音楽の専門家の中では従来のCDで音質は十二分とする方もおり、ハイレゾ支持者との間で論争があるみたいだ。 人の可聴周波数が20KHz以下となっているが、これは若い世代の聴力で、加齢で鼓膜が固くなるせいだろか歳をとると共に聴こえる周波数は低下してくる。私が子供の頃はテレビも真空管式だったので、スイッチを入れると「キーン」と言う発信音が暫く続いていたのを覚えている。この音はかなりの高音で、子供ながら心地の良い響きではなかった。この発信音が20KHz辺りだそうで、成人になると気にならなくなると言うより、聴こえ難くなってしまうのだそうだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年上の家内より当方の可聴周波数がやや低いのは、若い頃に猟友会に所属し、1発で映画の「ダーティーハリー」の使っていた44マグナムの3発分の威力がある、大物猟用のスラッグ弾をバカスカ撃っていて、その際発生する物凄い爆音と衝撃波で鼓膜が厚くなってしまったせいかもしれない。同じ様な話は、爆音の物凄いF1の開発をしていた経験のある方からも聞いた事がある。 <2016/2/4>CDを初めて聴いた時の印象は、素晴らしく澄んでいる音と感じた。デジタル・レコーディングの特徴はノイズがオーバーに言えば、全く聞こえない事にある。従来のアナログ音源ではLPレコードだと、レコード盤の溝に入っているゴミでパリパリと言った音が拾われてしまうし、テープでは磁性体微粉末が磁気ヘッドを通り過ぎる時に発するシャーと言う高音のヒス・ノイズが混じってしまう。アナログ音源の宿命であるノイズ対策として、カセットテープではノイズ・リダクションシステムが考えられた。一番ポピュラーなのがドルビーシステムだが、録音時に高域を持ち上げて録音し、再生時にはその分高域を抑えれば、高域成分のヒスノイズは必然的に低くなる。人間の聴覚は低音より高音に敏感なので、このヒスノイズを消すには合理的なシステムであった。 ドルビーシステムは舶来の技術なので、国内でもノイズ・リダクションの方法はかなり研究され実用化されたが、処理過程が複雑過ぎて、あまり原音をイジクリ過ぎると音は澄んでも再生音が色付きになってしまうので、シンプルで効果的なドルビーシステムが生残ったそうだ。音とノイズの比率をSN比(Sはシグナル、Nはノイズの略)と言うが、カセットテープで40〜60dB程度と言われる。dBとは常用対数を使って表しているらしく、数学の苦手な当方としては何回勉強しても、計算式はすぐに忘れてしまう。何でも人間の聴覚に合わせると、このdBで表すと都合が良いそうだ。 人間の聴覚とは蚊の羽音からレーシングカーの爆音まで、とても幅広く聴く事ができる。音圧で言うと両者の差は100万倍にもなるのだろうに、排気の爆音はウルサイが、人間はそれ程の差があるとは感じない。人の聴覚とは小さな音は大きく、大きな音は小さく聴こえる便利なシステムが組み込まれている。神様か仏様の計らいかどうか判らないが、聴覚にこの常用対数的機能が備わってこそ人間は何十万年もの間生残り、不便なく暮らせているのだ。 <2016/2/7>CDのSN比は96dBと言われている。この96dBの値は、なにやら難しい理論から来ていて、1bitあたり6dBのノイズ(信号2に対してノイズ1の比率)が出るらしく、16bitなので96dBとなるそうだ。よってハイレゾ音源の使う24bitだと、そのSN比は144dBとなるのだろう。カセットテープのSN比を50dBとすると、CDはどの位ノイズが小さいか考えてみよう。CDとカセットテープとのSN比の差は96-50=46dBとなる。6dBで2倍、20dBで10倍となるので、20+20+6=46をdBで計算すると、10X10X2=200倍となる。CDのノイズはカセットテープの場合の1/200にすぎないのだ。この差を見れば、初めてCDを聴いた時の澄んだ音に感動したのは当たり前である。 このスペックを見るとデジタル音源のCDの凄さは歴然で、それまでのカセットテープやLPレコードを一気に駆逐してしまったが、CDが全盛になると以前のアナログ音源の方が音が柔らかかったとか、長く聴いても疲れなかったとかの感想が聞かれる様になってきた。これらの感想に理論的な裏付けはなかったが、ハイレゾ音源の登場でアナログ音源の良さが少しだが解ってきた気がする。先に紹介したウォークマン・プロフェッショナルは、音質においてプロ用デンスケには敵わないものの、一般的なカセット・デッキを凌駕する程の性能を持っていた。そのウォークマン・プロフェッショナルでさえ、再生可能な高域周波数は15KHz程度であり、CDの20KHzに遠く及ばないものの、ミュージック・テープを聴いてみると感動ものの臨場感があるのだ。 <2016/2/15>話は前後するが前述のdB(デシベル)とは何かを書いておきます。日頃この値は騒音等の尺度で見聞きするだけで、馴染みのある単位ではありません。私自身、常用対数を使ったこの値を理解するのが苦手で、計算式もすぐに忘れてしまいます。参考文献を見ても、計算式より表を掲げている場合が多いので、計算はする必要はないでしょう。
dBは絶対値ではなく何倍かを表しているので、6dB(2倍)と20dB(10倍)を覚えておけば何とかなります。
また、足し算や引き算だけで何倍か何分の一かを計算できるので、便利と言えば便利です。例えば6dB(2倍)+6dB(2倍)=12dB(4倍)となります。
dBとはB(ベル)の1/10の事で、B(ベル)は電話を発明したグラハム・ベルの名前から来ていそうです。
彼が電力の送電効率を計算するのに考え出した計算方法ですが、電力の平方根が電圧や電流値になるのでと、一般人にとっては非常にややこしい限りです。10倍は0が1個(1X20=20dB)、100倍は0が2個(2X20=40dB)と、そのゼロの数を20倍すればdBになると覚えるしかありません。 | <2016/2/17>ややこしいdBの考察から、話を本題に戻します。アナログ音源のカセット・テープの音の評判の良い理由は、音色を決める成分の音の波形にあると思います。同じ曲をCDとミュージック・テープで聞き比べてみましたが、デジタル音源のCDの方が特にパーカッション等の楽器の音が綺麗に再生できていて、さすがに解像力は高いと思われます。ミュージック・テープは高域の再生可能周波数が低いせいか、それぞれの楽器の音が混然としていますが、歌手の吐息になるとCDでは聴こえない雰囲気をリアルに再生しているのには驚きました。 CDに刻まれている音の波形は、前述の通り階段状です。20KHzまでの高い周波数を再生できるので、シンプルな波形を持つ楽器の再生には十分な性能が出ているのでしょうけど、音色を決める波形となると16bit以上の細かさは表現できません。それに対してカセット・テープは、磁性体微粒子の持つ磁力の変化で連続的に無段階で記録していますので、歌手の吐息とかの表現ができるのではと推測しています。大げさに言えば無限bitですね。この辺りがCD16bit音源に慣れた世代に対して、微妙な音色の差を表現できる高bit数のハイレゾに感動を覚える理由ではないでしょうか。 ハイレゾ音源が如何に高bit数を使っても、波形で決まる音色に関してはアナログ記録媒体には敵わないのではと推測しています。同じ曲がハイレゾ音源であれば、是非聴き比べしてみたいですね。 続く、、、
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||